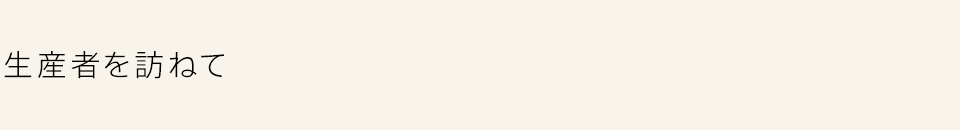
約300年以上前。元禄2年、高松藩藩主が朝廷の装束方御用を務めていた織物師・北川伊兵衛常吉に、新しい絹織物の製作を命じ、作られたのが保多織の始まりです。
以来、保多織は幕府への献上品としても使われるようになりました。
保多織の技法は、一子相伝の秘法として北川家で6代に渡り伝えられ、明治維新後、北川家の血縁にあたる岩部家がその技法を継ぎ現代に至ります。

高松市内の中心部、かつて高松城の城下町だった場所に岩部保多織本舗の工房はあります。
工房と店舗が一体となった建物の中は、棚一杯に保多織製品が並びます。
店舗奥の工房では、保多織を縫製するミシンのリズムカルな音が響き、店舗では訪れるお客さんと岩部さんの話声が聞こえる、なんとも心地いい空間です。

創業120年の岩部保多織本舗の4代目、岩部卓雄さんにお話を伺いました。

「1反、手作業で織り上げるのに大体8日間。手織りの発注があったときは、日中はお客様や電話の対応などで集中できないので、大体夜に作業します。」
店内におかれた織り機。この織り機は、遠方での展示の際に持参する織り機で、解体し、コンパクトに持ち運びができるそうです。

綿の保多織は、小巾の自動織機と、シーツも織れる大きな機械で織られています。
「機械とはいっても昔からずっと使っているものでしょ。糸の張り具合の調整など、この機械を操るのが大変なんです。調子をくずしたら修理するにも一大事。」
「代表もまだ小さいお子さんがいるため色々考慮してくれ、お母さん達にとってとても働きやすい職場なんです。」と笑顔で教えてくれました。
糸の張り具合、織り具合、すべて機械によって異なるため、目で、手で確認をする必要があります。そして、今ある機械を大切に使い続け、後世に残すことも重要な仕事の一つです。

織り機には糸が一本一本小さな穴に通され、それで経糸を操作して織り上げていく。この作業は展示の際に持参する織り機でも同じことです。
目を細めなければいけないほどの小さな穴。その穴に糸を通すのも、もちろん手作業とのこと。その大変さを想像し、驚いていると、
「別に驚くようなことではないですよ。昔から普通にしていたことなので。どれも特別なことではなく、昔の人たちが行っていた普通のことなんです。」
と教えてくれました。

保多織の特徴はこのワッフル状になった生地。
普通の平織りの布は縦糸と横糸をすべて交差させますが、保多織は3回平織りで打ち込んで、4本目の糸を浮かせる織り方にあります。こうすることで、生地に空気を多く含み、夏はさらりと涼しく、冬は暖かい生地となります。
保多織は使いこむほどに肌なじみがよくなります。肌に溶けこむようなその質感は、使った人だけが感じることができる、なんとも言えない気持ちよさです。
岩部家に保多織が引き継がれた頃に、それまで絹で作られていた保多織が木綿でつくられるようになります。
「絹は高級品。それを木綿に変えることでより多くの人に使ってもらえるようになった。僕はこの保多織のシーツを、全国の人に敷いてあげたい。そのくらい、この保多織は肌触りがいいんです。」
岩部さんはそうおっしゃいます。
岩部家に引き継がれたことで、私たちの生活に身近になった保多織。
一貫しているのは「より多くの人にこの心地良いものを使ってもらいたい」という本当にいいものを残していこうとする気持ちと、様々な人達にとって心地よい生活品を届けようという思いやりのように感じました。
取材の最中も絶えずお客さんがやってくる店内。
長年、岩部保多織本舗で寝間着を作っているお客さんや、自身の洋服、そして父親へのプレゼントを探しにきたというお客さんなど。
「ここのはね、一度使ったらもう他のものは使えなくなるよ」そう聞こえてきた言葉が、地元の人に愛され続けている何よりの証拠です。