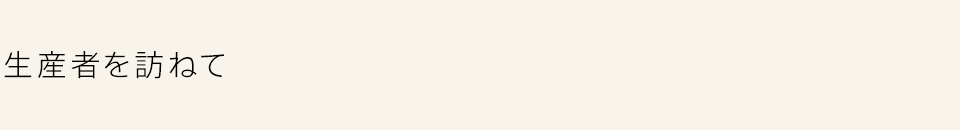
香川県には「香川漆器」がある。
漆器というと、輪島塗や会津塗が有名だが、実は香川県も漆器の産地であり、国の伝統的工芸品にも指定されているのだ。その歴史は江戸時代まで遡る。現在の香川漆器の原型は幕末から明治初期に活躍した漆工 玉楮象谷(本名:藤川為造)によって形作られ、その技術は彼の弟である藤川黒斎(屋号を文綺堂)らによって受け継がれた。そして、その文綺堂から分岐して設立されたのが、今回取材させていただいた一和堂工芸株式会社(以下、一和堂)だ。

今の浅野社長は3代目で、お祖父さまが一和堂を設立。
お祖父さまはもともと百姓だったが、兄弟も多かったため石川県加賀市の山中(漆器の産地)で修業し、帰郷後漆器屋を始めた。
戦時中は軍からの依頼で漆器を作っていたこともあったそうだ。当時は金属回収令などもあり物資が不足していたため、さぬき市長尾で製造された竹を編んだものに漆を塗り重ねて食器にしていたようだ。

浅野さんは平成12年に会社を継いだ。当時は経営的に厳しい局面もあり、お父さまからはやめても良いといわれていたが、お祖父さまの代からやってきているものをなくすのはもったいないと思い、やらせてほしいと申し出て会社を継いだ。
社長に就任して取り組んだのが若年層向けの商品開発だった。就任前から若い世代の漆器ばなれは課題としてあった。昔は各家庭に漆器があり今よりも身近な存在だったが、核家族化が進み、漆器を使っていた世代から若い世代へ継承の機会が減り、ライフスタイルの変化もあり漆器は身近なものではなくなってしまった。

そんな状況を打開するために取り組んだことの一つが価格を抑えること。
漆器が身近ではない世代にとって価格が高すぎればハードルが上がってしまう。しかし、だからといって品質を落とせば本末転倒だ。そこで香川県ではあまり行われていなかった「塗りたて」という技法を取り入れることにした。これは油を含んだ漆を上塗り(漆器製作ではいくつかの工程があり、下地、下塗り、中塗り、上塗りなど。字面の通り上塗りとは塗りの最終工程にあたる)に使う技法だ。呂色仕上げ(詳細は後述)に比べると工数が減るため、コストを抑えることができる。その分販売価格も抑えられるので少しでも漆器を手に取ってもらえるのではないかと考えたそうだ。「塗りたて」の仕上がりは柔らかでふっくらした漆らしいものになる。
香川県で一般的な呂色仕上げでは、上塗りのあとに研ぎと艶上げという工程が加わる。これは漆器の中でも高級品に使用される技法だ。表面が鏡面のようにピカピカになる。しかし、これは日常使いのものというより、それこそハレの日など特別な時に使うようなものに使用する技法だ。香川漆器の祖である玉楮象谷が、幕府に献上する漆工芸品を製作していたことを考えれば、呂色仕上げを採用していたのも納得である。
この「塗りたて」という技法、工数が減ると書いたが、それでは誰でもできる技法かというと決してそうではない。むしろとても難しい技法だ。呂色仕上げとは違い表面を研がないため、塗ったその状態がそのまま完成品となる。漆は粘りがあるため刷毛目が極力目立たたないように、また埃や気泡が付かないよう滑らかな仕上がりにするには熟練の技が必要だ。
また乾燥の工程でも苦労したそうだ。当初は商品として店頭に出せるようになるまでにはかなり試行錯誤の連続だったが、いまでは一和堂の戦力になっている。
デザイン面でも様々な取り組みを行った。一和堂では香川県にゆかりのあるデザイナーとのコラボ商品を、デザイナーズシリーズとして展開している。これは県の漆器組合とデザイン協会の取り組みとして企画されたもので、参加するかどうかは各企業の判断だったが、浅野さんは「とにかく挑戦してみる」の精神で様々なデザイナーとコラボを行った。デザイナー側からのオファーも結構あったようだ。
ただ、コラボ商品の開発は必ずしもスムーズにいったわけではなかった。デザイナーのこだわりが実際の製作の場では工数やコスト面で採用するのが難しい場合もあり、デザイナーとの間で侃々諤々の議論になることもあったようだ。
漆は「乾燥」させるのに気をつかう塗料なのだ。乾燥というと熱や風をあてて水分を蒸発させるが漆の乾燥には温度と湿度が重要で、通常の乾燥とは異なる。(温度:25度程度、湿度:75%程度)
そのうえ、1度に厚く塗ってしまうと「縮み」といって表面がシワシワになってしまう。絵具と同じような感覚で扱うとうまくいかない。こうした特性ゆえにデザイナーとの間で認識の違いが表面化することもあったようだ。
こうしたやりとりを経てデザイナーズシリーズは生まれた。
商品開発で浅野さんが心掛けていることがある。
「人と話をすること」
なかでも若い人と話をすることは商品づくりのヒントになることも多い。なにげない会話の中で生まれた商品も少なくない。
高松はお盆の木地の産地でもあるため、祝いごとの贈り物としてもよく使われていた。そのため香川県下の各家庭には、漆塗のお盆が1枚といわず複数枚はあるような状況だった。そうした背景もあり、お客さんからもお盆以外で何かいいものはないかと聞かれたという。そこでカップを色漆で塗ってみたところ気に入ってもらえたそう。当時は独楽塗の朱、緑、黄の3色だったが、いまでは12色でカップだけでなくスプーンやフォークなどバリエーションが豊富だ。

県産品コンクールで最優秀賞も受賞している薔薇の器も何気ない会話から生まれた商品の一つだ。「女性ってバラ好きだよね」という日常の中での会話から、漆器で薔薇をイメージした商品を作ってみようということになった。結婚のお祝いや内祝いとしてお求めになる方も多いそうだ。

こうした様々な取り組みについて浅野さんは、
「何か出来たらいいなと思ってとにかくトライしてみる。」
取り組みを振り返って
「やってよかった。面白いし、なにより(コラボなどは)自分にはない発想を得られる。それは一和堂としても財産になる」
東京での展示会に出展した際、お父様の代から一和堂を知っている方が、イメージがガラッと変わっていて驚いていたそうだ。
様々な新しい取り組みを行う一方で、お祖父さまの代から塗りをしっかりするということを大切にしており、職人にも自分が買いたいと思わないようなものは作ってはいけないと口を酸っぱくして言っている。
コストカットのために下地などで手を抜いたとしても、出来上がったものは見た目からでは玄人でもわからない。しかし、実際に使っていると手を抜いているものは、そうでないものと比べるとやはり塗装の剥げや木地の欠けなどが生じやすくなる。だから、見えないところであっても決して手は抜かない。
デザインは時代とともに変わっても、基本的なモノづくりの姿勢は変わらない。
新しいことへの積極的な挑戦と丁寧な伝統的なモノづくり、伝統と革新の両輪で歩む一和堂の今後から目が離せない。
最後に一和堂を支える工房の様子を少しご紹介。

両手と足でささえて作業 お祖父さまの代から続く一和堂の塗りのスタイル
写真(上)は馬の毛が使われた刷毛で生漆を木地に刷り込んでいるところ。結構な力仕事だ。

高橋さんは一和堂に入社して38年のベテランだ。漆の仕事がしたくて一和堂に入社。天職だと思ってこの仕事をしている、そう仰るその瞳からは職人としての誇りと、本当に漆の仕事が好きなことが伝わってきた。

最年少の髙木さんは入社して8年目。地元の工芸高校を卒業後、香川県漆芸研究所(県が運営する香川漆芸を継承するための教育機関)に入所。そこで3年間香川漆芸を学び、修了後日常使いの漆器づくりの道に進むため一和堂の門を叩く。今は職人として漆と向き合う日々をおくる。
塗の際お盆などを支えるために脚の上に置いている布は漆を吸ってカチカチになっていた。

一和堂の店舗では栗林庵オンラインショップで取り扱いのない商品もご購入いただけます。要事前連絡。詳しくは一和堂のwebサイトをご確認ください。
