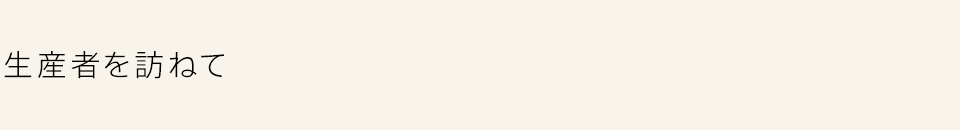

四国八十八箇所霊場七十九番札所「天皇寺」のすぐ近くでところてんを作り続ける、清水屋さん。涼しげな湧き水の音と鮮やかな木々の緑が美しいこの場所には、涼を求め多くの人が訪れます。

清水屋さんがある「八十場(やそば)」という地名は、景行天皇の時代の「悪魚退治」という伝説に由来し、悪魚と戦い、毒にやられた88人の兵士がこの地の水を飲んで元気になったと伝えられています。この伝説から「八十蘇生場(はちじゅうそせいば)」といわれ、「八十八(やそば)の水(八十八の清水)」と言われるようになりました。
また、配流された崇徳上皇が亡くなった折には、腐敗を防ぐため、涼しい木陰でこの地の水を使用したという歴史も残っています。

今回お話を伺ったのは8代目、筒井雄一郎さんご夫婦。
清水屋さんがこの地でところてんを作り始めた作り始めたのは江戸時代にまでさかのぼります。そのころ書かれた「金毘羅参詣絵巻図」には「心太(ところてん)・西瓜(すいか)・焼酎の商いが行われていた」と書かれています。
明治時代には、画家の尾崎秀南が「弥蘇場(やそば)の湧泉」と描いており、昔からこの地を人々が大切にし、守り続けてきたことが分かります。
今はこの地も海沿いから離れていますが、昔は海が近かったようで、近くには船着き場のようなところも残っており、ところてんの材料となる天草が採れていたそう。
豊かな湧き水と近くで材料が採れるという立地から、ところてんづくりが始まったのではないかと考えられています。
現在も湧き水をところてんを冷やし固める時に間接的に使っているそうです。

ところてんを作るには、水がきれいであることが大前提。加えて、ところてんは夏に涼を得られる食べ物なので、涼しい場所というのも必要になりますが、清水屋さんの場所はその条件にぴったりの場所です。
近くには四国八十八箇所霊場七十九番札所「天皇寺」があり、ちょうど四国遍路の裏参道にあたるため、昔から清水屋さんで休憩をするお遍路さんも多くいるそうです。お遍路さんが休憩をすることで、清水屋さんのところてんは各地へ広まっていったのかもしれません。

現在のお店の営業は毎年3月末から11月いっぱいまで(10月、11月は日・祝日は定休)ですが、忙しいのはやはり8月。香川県内のお客様が多いそうですが、お盆の時期などは県外から帰省をして食べに来られる方もいて、県内外問わずたくさんの方がいらっしゃるそうです。

おやつの時間(14時~16時頃)に食べに来られる方が一番多いそうですが、満腹感を得られるのと食物繊維も多いことから、実は、お昼ご飯前にところてんを食べてからご飯を食べに行く人もいるそうです。

元々は酢醤油だけだったという味も、今では様々な味が用意されています。
お遍路さんや、全国各地から来られるお客様から、「この地方はこうやって食べるのよ」とご当地の食べ方を教えてもらって、味のバリエーションをどんどん増やしていったそうです。
一番人気はやはり酢醤油。最近はきな粉と黒蜜という「くずもち風ところてん」も人気です。
時代や食文化の変化に合わせて色々な味も考えているそうです。
また、30年ほど前からは持ち帰り用のところてんの販売を始め、このおかげで、さらに遠方の方にも知ってもらえるようになりました。

清水屋さんのところてんは、国産の天草を使用しています。国産の天草は、採れる量も採る海女さんも減っており、年々価格が上がっているそうです。
春に採れる「春摘み一番草」が一級品と呼ばれるそうですが、清水屋さんはこの「春摘み一番草」を使用しています。
本来、天草は深い赤色ですが、天日干しをすることによって薄いベージュ色に変わります。天草と水を鍋で煮詰め、煮汁を濾した後に固めたものがところてんです。

「この水がなかったら、うちもなかったのかなと。大切に残していかないといかんなあと思います。」と笑顔で語ってくれた筒井さん。
材料もこだわり、手間暇かけて創業当時からの変わらない製法を守り続けている清水屋さん。
暑い夏の日、遠い昔に思いを馳せながら、ひんやり冷えたところてんを食べてみてはいかがですか。

「サヌカイト」は固い棒などでたたくと澄んだきれいな音がする天然石です。世界で最大の産出地は香川県で、すでに旧石器時代には矢ジリや石刀として狩りなどに使われており、江戸時代には音のなる道具としても使われ始めたそうです。1981年に地質学者のヴァインシェイクが讃岐(さぬき)の岩の意をこめて「サヌカイト」と名付けたと言われ、1964年の東京オリンピックの開会を告げる合図としても使われました。
今回はサヌカイトを使用した製品づくりに取り組む平井石産の事務所兼作業場にお邪魔して平井美恵子さんにお話をうかがいました。
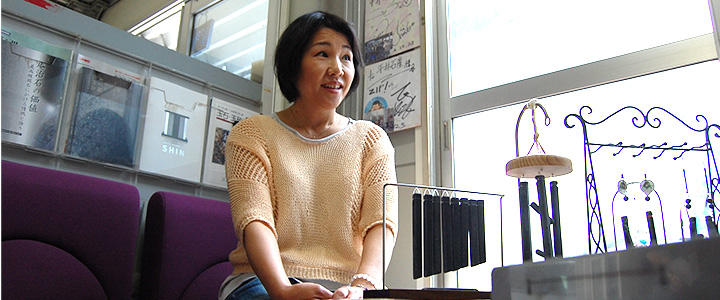
平井石産はもともと石の採掘から始まり、墓石をメインで扱う石材店でしたが、坂出ブランドの発足がきっかけで2012年から新たにサヌカイトの商品の販売を始めたそうです。現在は美恵子さんと社長のお二人で全てを切り盛りされていて、サヌカイト製品はなんと主に美恵子さん一人で作られています。
もともとは表面がザラザラしたサヌカイトの原石を何枚もの石板状に切断します。そしてその1枚の石板をさらに細い棒状に切断します。最後に角を面取りして表面を磨いて風鈴やチャーム※が出来上がります。

最初はグラインダーを使って手作業で石の切断を行っていたそうですが、サヌカイトは欠けやすく加工が難しいのでまっすぐきれいに切れずよく割れていたそうです。自作でグラインダーを固定する台を作ったりと試行錯誤の末、今は平らな円盤状の歯がついた大型の設置式の機械を使っています。歯の大きさが機械ごとに違うので削りたい石の大きさによって機械も使い分けます。機械を動かすと大きな音を出すため大声で叫ばないと会話もできないようで、その様子はまるで喧嘩のようとのこと(笑)。
演奏用の石琴は複数のチューナーを使い、微調整を繰り返すそうです。

平井さんによるとサヌカイトの魅力はそのゴツゴツとした無骨な見た目と音とのギャップだそう。今回お話を伺ってみると音に対しての繊細なこだわりなど、女性が作られているのも納得だと感じました。
「讃岐」「石」「音」にちなんで新たに「SANUKITONE」というブランドを立ち上げ、まだまだ全国的に知名度の低いサヌカイトをより多くの人に知ってもらいたいそうです。
※チャームは栗林庵店頭のみの販売となります。

昔ながらの製法、杉桶で自然発酵させて造る醤油、鶴醤(つるびしお)。
再仕込みという醤油を造る製法で造られた鶴醤は、約4年の歳月をかけて造られます。塩味も角がとれ、まろやかで旨味の凝縮した濃い味わい。
いつもの食べ方以外にも、そのままワサビと併せて焼き肉のタレに、バニラアイスにかけて食べても美味しくいただけます。

鶴醤をはじめ、杉桶で自然発酵の醤油を造っているのが小豆島安田地区にあるヤマロク醤油さん。高松港からフェリーで約1時間、瀬戸内海では淡路島に次ぐ第2位の面積の小豆島は、かつては島塩とよばれる全国でも有数のブランド塩の産地でもありました。また海上交通が盛んだった瀬戸内海。塩以外の材料は海を越え運ばれ醤油が造られるようになりました。
今でも小豆島には島の中に20 軒以上の蔵が残っています。特に今でも醤油蔵が多く残る安田地区。この川沿いにヤマロク醤油さんはあります。
今回お話を伺ったのは5代目、山本康夫(やまもとやすお)さん。「この5代目も正確な記録上の5代目であって本当は6代目、7代目かもしれません。」そうおっしゃるほど長く歴史のある醤油屋を守る5代目です。

「醤油屋は儲からんから継がんでええ。」
そう父親から言われていた康夫さんですが、島に戻りたいという想いと、大学卒業後の就職先で垣間みた食品業界への憤りから蔵を継ぐことを決意。
「意気込んで帰ってきたけれど帳簿を見て愕然としました。」
それだけではなく、父親が『地獄のもろみ混ぜ』と呼んでいた春から夏にかけて活発に発酵するもろみを混ぜる作業。もろみの発酵熱も加わってサウナ状態の中、手作業で桶をかき混ぜる作業は毎日欠かすことなく行ないます。
この時期はそのハードワークから体重が6~9kgも減るそう。蔵の維持にも莫大な費用がかかることがわかってきました。
これだけ大変なことが分かっても続けている醤油造り。それは、蔵に生き続ける菌達に美味しい醤油を造ってもらうため。

杉桶は醤油蔵に住み着いている酵母菌や乳酸菌でびっしりと覆われています。この菌は蔵ごとにいる種類も量も異なり、造り出す醤油の味を変えます。
「醤油を造っているのはこの蔵に住み着いている菌たち。僕は菌が醤油を造ってくれるのを手伝っているだけ。」と山本さんは言います。
だからこそ、地獄のもろみ混ぜを行い、昔からの蔵を維持しています。
「うちの蔵の菌達はね、女性のお客さんが来ると特に元気になるんです。」
その言葉通り、階段を登って桶を覗き込むと、不思議なことにそれまで発酵途中の桶からプチプチと泡が上がる音が大きくなっていきます。まるで見学にきたことを歓迎するかのように大きな音が響きます。
「科学的な根拠はないけれど、めんどくさいなと思って仕事していると菌達に伝わってしまう。逆に気持ちを込めるとそれが菌に伝わって醤油の味がぐんとよくなる。」
そう、醤油を含め食べ物をつくるということは、本来は自然とそして生き物と向き合う仕事なのだと山本さんの話を聞いていてつくづく感じます。

「小豆島に杉桶は約1050本。日本全国で発酵調味料に使われている杉桶は約4000本、その半分くらいが醤油、味噌に使われているとしても約2000本。日本の杉桶の約半分が小豆島にあることになる。こんなに杉桶が密集している地域って他にない。」
発酵菌や乳酸菌が生きていくためにはこの杉桶が欠かせません。けれどもその杉桶は年々減ってきています。
「うちの杉桶を桶職人さんに見てもらって、もう既に杉桶の寿命とも言われている150年を経過していることが分かった。幸いな事に大切に使えば僕の子供の代までは使えることが分かったけれど、子供の代で終わり。そもそも、この大きな杉桶をつくる職人さんは全国にも3人しかいない。」
中古の杉桶でも試したが、その桶に住んでいる菌の影響で上手くヤマロクさん蔵の菌が住み着いてくれない。やはり新しく杉桶を造らなくてはならない。
その思いで新しい杉桶を発注した時、職人さんは「戦後、醤油屋から注文が来たのは初めてだ」と職人さんも山本さんも驚いたそう。その言葉は、日本全国で現存している杉桶が古くなっていること、そして杉桶自体の数が減ってきていることの証です。
けれどヤマロクさんの杉樽を見てくれている、山本さんが師匠と呼ぶ大阪の職人さんは、2020年には職人を引退すると宣言していたそうです。
「もうねこんな大きな杉桶を造れる人自体がいない。それは、最近、和食が無形文化財にもなっていたけれど、本物の和食の味が消えてしまうということなんです。」
そこで山本さんは2012年、自分自身で桶を造ることを決断します。地元の大工さんと大阪の職人さんの元へ修行に行き、造り方を一から勉強し、実際に桶を造りあげました。もちろんその過程は今回の取材では納まりきらない位のストーリーがあります。

「僕らの蔵の醤油がちゃんと売れたら、真似して杉桶で醤油を造ろうってところが出てくると思うんです。その時に、地元の大工さんが桶を造るのが仕事になる。桶を造ることが普段の大工仕事よりもいい収入につながれば、桶屋になろうってやつが出てくるでしょ。」
100年先を見据えたヤマロクさんの醤油造り。
「長男は醤油屋、次男は桶屋になってもらいたい。」
「本物の味」と簡単に言ってしまいがちだが、こんな風に全てをかけて日本の味を守っている人が香川にいて、今日も醤油を造っている。ぜひ一度、蔵に行って、そしてヤマロク醤油さんの醤油を味わってもらいたいと思います。

小豆島の南側、日当りのいい池田地区。その池田の玄関口、池田港から徒歩数分、そこに東洋オリーブさんの工場と畑があります。

今回、お話を伺ったのは営業部長の藤塚隆さん。
自社の畑を持ち、苗木生産、栽培、食品製造、化粧品製造、販売までを手がける東洋オリーブ。藤塚さんも入社したての頃は製造の仕事に携わっていたそうです。

昭和30年、今から約60年前に小豆島でオリーブの栽培を始めた東洋オリーブ。現在は小豆島池田地区に12ha、豊島に13ha、約3万本のオリーブの木を育てる畑があり、その広さは日本最大の面積を誇ります。
始まりは戦後間もなく、一時は日本の三大億万長者の1人とも呼ばれた南俊二氏が海運王オナシス氏と食事した事がきっかけです。南氏は釣ったばかりのイワシを油で揚げたシンプルな料理の美味しさに釘付けになります。その揚げ油がエキストラバージンオイル。ギリシャ出身のオナシスの話を聞くうちに「この感動を日本に伝えたい!」という想いが強くなり、ギリシャから帰国後、日本でオリーブ栽培を行なっている場所を探して見つけたのが小豆島。
何も無いところからスタートしたオリーブ栽培は、山を開墾することから始まります。最初の頃は豚や牛を飼いながらその堆肥で土づくりを行ないました。
「この事業は半世紀かかる。50年赤字が続いてもいいからひ孫の代に残していける事業にしよう。」そう語り、半世紀先を見据えたこのオリーブ栽培の事業は、48期目にようやく黒字になりました。
地域密着型の会社であること、大きくしなくていいから、きらりと光るものを大切にコツコツと積み上げていくこと。東洋オリーブは、初代、南俊二氏の想いを今でも大切にしている会社です。

東洋オリーブには、日本で最大の遠心分離法の採油工場があります。実は東洋オリーブが工場を作るまで小豆島にはオリーブの採油工場は有りませんでした。民間初のオリーブ工場はそれまで農業試験場しかなかった小豆島内で、東洋オリーブ自社以外の採油や加工なども請負い、小豆島のオリーブ栽培の縁の下の力持ちとして活躍します。
長年培った高い採油技術を使用し、地中海から仕入れたエキストラバージンオリーブオイルを日本人の好みに合わせて精製しています。

右が精製前のエキストラバージンオイル、左が精製後のオイル。
一見、なんだかもったいない!と思ってしまいますが、オリーブオイルの販売を始めた当初、オリーブ独特の香りは日本人の味覚には馴染みづらかったため、この精製オイルが生まれました。
オレイン酸を多く含みながらも、サラサラと透明なこのオリーブオイルは癖がなく普段使いや、揚げ物に向いています。
毎月第一土曜日には自社の工場で精製したオリーブオイルの計り売りもしており、近所の方が朝早くに並んでいたり、船に乗って買いに来られる方もいたりするほどの人気です。
毎年11 月には小豆島でとれたオリーブオイルの販売も始まります。料理によってオリーブオイルを使い分けてみる。そんな贅沢なことも出来てしまいます。
小原紅早生とは、香川特産のみかん。
小原さんの畑で「宮川早生」という品種が枝変わりして偶然生まれた品種です。
真っ赤な外皮と濃厚な甘みが特長です。


かわいらしいパッケージの小原紅早生の缶詰。
ふたを空けるとぎっしりときれいな実がたくさん入っています。

香川県財田町、竹林が茂る山間部に讃岐缶詰の本社はあります。
筍の産地でもあるこの地域。昭和4年、地元の特産品の筍の加工を目的に地元の人たちで農業物加工販売組合として設立されました。昭和27年には現在の讃岐缶詰株式会社として設立。現在は財田の本社工場のほかに、三野、善通寺、秋田県にも工場があります。

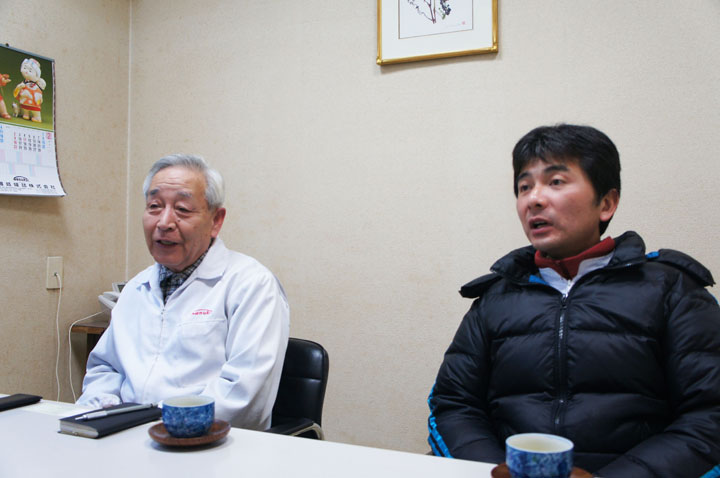
約50種類ほど、多岐に渡る農産物を加工する讃岐缶詰。
フレッシュな青果を収穫されたその時期に加工します。
「自然相手だからなかなか計画通りにはいかないですよ。
それに味も皮の厚さも糖度もその年々で変わってくるから、缶詰作りには様々な知識と経験が必要です。」
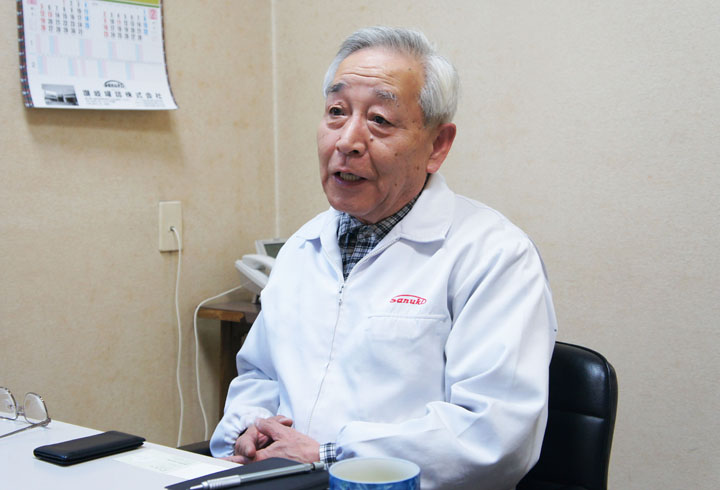
約45年讃岐缶詰に勤めている大西さんは戦前からの従業員の人とも多く仕事をしてきました。
そのときから何度も教えられていたのがこんな言葉。
「なによりも信頼が大切。」
「そして大事にしている考え方は生産者もいい、働く人もいい、お客さんもいい、三方よしの会社であること。」
そんな教えが基板にあったからこそ、安価な外国産の原料が多く出回り始めても国産の材料にこだわり商品を作り続けました。それは会社が大切にしている信頼と三方よしの考えを今でも大切にしているからに他ありません。
OEM商品を中心に展開している讃岐缶詰。発注を受け続けているのはやはり確かな技術と信頼があるからこそだと感じました。

真っ赤な小原紅早生。取材に伺った1月が丁度収穫時期。たくさんの小原紅早生がコンテナで運ばれていました。





果実は更に大きさごとに手作業で選別し缶につめられます。
スタッフの人たちはそれぞれ担当行程が決まっているそうで
「どの人もね、もうずっとこの仕事に携わっていてベテランがとっても多いんです。」
スタッフの人たちは勤続年数も長いそうで、工場を案内してくれた方の少しはにかんだ、でも自分の仕事に誇りをもっているような笑顔が印象的でした。