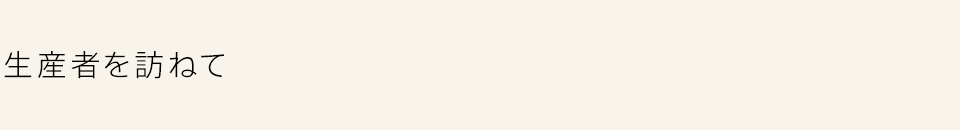

木目を感じるシンプルな美しいフォルムの器は、そのままずっと眺めていても飽きない佇まい。
まだ使用年月の短い肥松の器は、少し手に残る独特の触感と木ならではの暖かみを感じます。
日本は国土の約67%、3分の2が森林で覆われており、私たちの暮らしと木々の関わりは古くから切っても切り離させないものでした。
もちろんそれぞれの地域ごと風土に適した木は異なります。
香川といえば、全国の約8割のシェアを誇るほどの盆栽の一大生産地。
盆栽の樹種として昔から使用されているのが黒松です。
その黒松の中でも、樹齢300年以上の油分をたっぷりと蓄えた木の中心部が肥松。
肥松は100年程の時間をかけて色が飴色に変化し、手触りも使用するごとに良くなるという特製を持っています。「親子孫三代続くことでその家が完成し、栄える」とされていた日本の考え方や、松竹梅にも表現される松そのものが持つ吉祥の象徴的な意味合いも相まって、肥松は高級木材として重宝される木材でした。
香川では黒松の育ちやすい環境があり、昔から良質な肥松が採れていたため、大阪や京都など広く出回っていました。
またろくろ仕上げの肥松の木工品も江戸時代から作られており、茶人などに愛好されていたようです。

そんな肥松を使用した木工品を作っているのが、高松市内に工房をもつ有限会社クラフト・アリオカです。
田んぼの広がる、讃岐らしい細いクネクネとした小道添いにその場所はあります。
讃岐式のろくろで挽いた木工品を今でも作る工房です。

「父が木工を始めたのは戦後まもなく。終戦後、兄弟たちが戻ってきて食べるものがないので木の加工を仕事にしたのが始まり。」と工房の成り立ちを教えてくれます。
今回お話を伺ったのは、2代目肥松の伝統工芸士有岡成員さん。

最初は輸入木材を加工し外国に売っていましたが、やがて国内の木の加工をろくろで始めるようになります。
その際に、低調しかけていた香川の漆芸を再興させた人間国宝の磯井如真氏に腕を買われ、氏に提案され作り始めたのが肥松との出会い。
肥松は油分を多く含む特製のため、加工が非常に難しく、高い技術が必要となります。
また肥松の器の制作を後押ししたのが、香川のかつての知事、金子正則氏。
仕上げの油に酸化しにくいオリーブオイルを使用するようアドバイスを受け、いまでもクラフト・アリオカさんの作る肥松の仕上げはオリーブオイルです。
そんな偶然の出会いが重なり、幻とまで呼ばれていた肥松が、今、再び私たちでも手にできるようになりました。



松脂の多い肥松は、ろくろで削っていくと顔中が木屑だらけになってしまうほど。
有岡さん曰く、死んだ木を使ってもだめで、生きているうちに切り出した木でないと、この肥松独特の時間による色の変化は生まれないのだそうです。
しかし、残念な事に、樹齢300年を超える黒松は現在ほぼ入手できない現状。
もしあったとしても、切り出してから20年間以上は寝かせないと使用できないため、「今ある父親の代のストックを使っていくしかない」と有岡さんは語ります。

材料である肥松も、天井付近の軸からベルトを引いた横向きに座るロクロの造りも、讃岐で受け継がれていたもの。
「壊れても人を傷つけることの少ない”木”。
作られているものは人にやさしいものが多い。」
時間の経過と共に味わいが増す、有岡さんの作る器。
日々の暮らしに寄り添うずっと手元に置いていたい讃岐の逸品です。

手まりは1000年以上の歴史を持つ日本の玩具のひとつ。
平安時代から蹴鞠として貴族に親しまれており、長い間上流社会の人々のものでした。
江戸時代に入ると「讃岐三白」の一つ、木綿の生産が全国的に盛んになり、広く民間に浸透します。
糸の色やかがり方に工夫を凝らし、全国でそれぞれの地方独特の作り方・デザインが女性の手によって受け継がれてきました。
しかし、明治になりゴムが普及するとともにゴムまりが主流となり姿を消していきました。
そんな手まりに着目したのが讃岐かがり手まり保存会の生みの親、荒木計雄さんご夫妻でした。
荒木計雄さんは栗林公園内にある讃岐民芸館の設立を香川県に提案し、展示収集の為に全国を奔走した人物です。
「義父自身は、美しい事以上に身の回りにあるもので玩具を作り、おばあちゃんの手から子供にあげていたという、手まりのあり方そのものに魅力を感じていたようです。」
そう語るのは、今回取材させて頂いた、荒木ご夫妻の遺志を受け継ぐ荒木永子さん。
荒木永子さんがまり作りに使う道具は荒木ご夫妻から引き継いだものです。
みかんの空き缶に、大きな布団針、材料も籾殻、草木染めの木綿糸、和紙と、かつて日本の生活の中に当然のように存在していたものばかりです。



草木染に使用するものも、かつて日本の暮らしの中にあったものばかり。
今は、集められるものは自分たちで集め、入手が難しくなった植物は漢方屋さんなどを通じて入手するそうです。
荒木計雄さんが讃岐かがり手まりの調査を始めた当時、讃岐の特に綿花が盛んだった西讃地方には、手まりを作れる人はほとんどいませんでした。
そこで民芸運動の先輩である丸山太郎氏の叔母にあたる人物から、かがり技法の指導を受け、また木綿糸の植物染めは民芸運動家で染織家の外村吉之介氏などに教えを受けながら、讃岐の手まりを復活させ、これを讃岐かがり手まりと名付けました。
1983年、荒木計雄さんの出身地である観音寺市で讃岐かがり手まり保存会を設立。特に計雄さんの出身地の隣町は観音寺市豊浜地区といい、最盛期には20社以上の製綿所が軒を連ねていた綿の一大生産地でもあります。
設立当時、計雄さんの奥様の八重子さんと2人の妹さんで作っていた手まりは、やがて地域の人々にも広がっていきます。
現在、讃岐手まり保存会は事務所を高松市内へ移動し、東京の教室も含め、手まりを楽しむ人、手まり作りに携わる人は300~400人ほどです。
作るほどに奥が深いものでありながら、入口は広く、多くの人に楽しんでいただける伝統工芸、それが「讃岐かがり手まり」です。


讃岐かがり手まり保存会が大事にしている事は4つ。
この4つは昔、人々に親しまれていた手まりである事を満たす条件です。そしてそれは、模様や色合わせにはルールがある訳ではなく、作り手がその季節や自分の感性に合わせ、形を作っていく楽しみがあるということです。
手まりを作る際に一番時間がかかるのが色合わせといって、木綿糸の組み合わせを決めていく作業なのだそうで、ここに作り手の個性が現れます。
作り手がじっくり無心で向き合い丁寧に作られた手まり。
そこには作り手の想いと、木綿糸を草木染めで染める時間、ひと針ひと針糸をかがる時間、色合わせを決める時間、たくさんのかつて日本の暮らしの中にあった、丁寧な時間が讃岐かがり手まりには詰まっています。

荒木八重子さんの作った手まり。
八重子さんはこのベーシックな菊模様が好きだったそうです。

荒木永子さんが考えだした香手まり。
土台手まりもかわいらしいという先入観のない工夫から生まれました。
荒木永子さんは言います。
「讃岐かがり手まり保存会を引き継ぐ中で大切にしているのは『続ける事』。
それは困難な事ですが、作り続ける事、好きでい続ける事、こだわり続ける事。
この3つを大切にしながら、次の世代にバトンタッチできるような関わり方をしていきたいです。」
そう語る荒木永子さん自身がだれよりも手まりと向き合う時間を楽しみ、手まりのかわいらしさに愛着を感じているのでしょう。

「讃岐三白」とは、江戸時代に特に盛んだった讃岐の3つの産業である砂糖、塩、綿を総称した言葉です。
その砂糖とは和三盆の事です。糖蜜を抜いた白砂糖は当時、非常に重宝され、高松藩の特産品として全国に知られるようになりました。
名前の由来は3回盆の上で研いで作られるからとも言われています。
「研ぐ」とは盆の上で砂糖の結晶をより細かくして、糖蜜を抜けやすくするための作業の事です。何度も研がれる事により口に入れると、ほろほろと砂糖が溶け出すやわらかいまあるい食感を生み出しています。



讃岐和三盆の老舗、三谷製糖が位置するのは東かがわ市馬宿。
徳島とのほぼ県境、目の前に瀬戸内の穏やかな風景が広がる阿波街道沿いに三谷製糖はあります。
三谷製糖の創業は1804年。
約200年もの歴史をもつ三谷製糖は増改築を行っていますが、基本的には創業当時そのままの建物と道具を使っています。国の重要有形民俗文化財にも指定されている製糖器具をはじめ、本舗主屋や旧牛舎なども国の登録有形文化財になっています。
取材に訪れた際、8代目女将さんがゆっくり、それでいて凛とした口調で三谷製糖について教えてくれました。
讃岐和三盆の歴史を辿ると、薩摩の黒砂糖へとつながります。
江戸時代初期、砂糖は日本の中では薩摩で作られる黒砂糖が主流でした。やがて幕府は国内での製糖を奨励するようになります。高松藩では藩医の平賀源内がその役を命じられたものの、良質のサトウキビを入手できず、弟子のそのまた弟子の向山周慶までその役は引き継がれます。
時を同じくしてその頃、遍路で行き倒れた旅人を向山周慶が助けます。この出来事に恩を強く感じた旅人は再び、ひっそりと小舟に乗って讃岐の地へサトウキビの種キビとともにやってきます。
そう助けた旅人は奄美の人。
当時、門外不出のサトウキビを藩外へ持ち出す事は重罪です。
「それほどまでに恩に感じていたんでしょうね。」
こうして讃岐の地でサトウキビは、非常に運良く、お米が出来にくい土地にしっかりと根をはります。

現在も三谷製糖周辺にはサトウキビ畑があります。
高松藩でサトウキビが育ったものの、風土が違うため薩摩で作られる黒砂糖の様に固く甘味が強い砂糖にはなりませんでした。
向山周慶をはじめこの土地の人々は、薩摩の黒砂糖に負けない美味しい砂糖の作り方を考えます。そこで思いついたのが砂糖から糖蜜を抜く方法でした。
「当時の記録を見ていく、和三盆の製法を生み出すのに数十年もの歳月を要したようです。道具も、製法も全て自分たちで考え、生み出されたのが和三盆なのです。」
そのときに考えだされた製法を、地元の庄屋5軒が門外不出の製法として引き継ぎます。それが1804年。その5軒の中で唯一現在も経営を続け、その当時からの門外不出の製法を守り作り続けているのが三谷製糖です。
「薩摩の人たちも和三盆の作り方を真似したそうですが、同じにはならかったそう。この土地で作ったさとうきびでないと、この和三盆はできないんです。」

和三盆へ仕上げて行く際に使用されるのが国の重要有形民俗文化財にも登録されている押し舟です。
サトウキビの種キビを土の中へ生けるのは11月中頃です。
春、職人さんが畑に赴き、サトウキビの植え付けの作業も行います。
1年かけて地元の農家さんが育て、12月に収穫。この時期が最も忙しい時期だそうです。
収穫したサトウキビを絞った汁はその日のうちに炊き上げ、白下糖という原料糖にします。
「白下糖作りが始まるこの時期は本当に忙しいです。」
収穫したサトウキビを白下糖へ仕上げる作業は、長いと1月下旬まで続きます。そうして出来上がった白下糖を1年かけて少しずつ和三盆へと仕上げて行きます。
和三盆へ仕上げて行く際に使用されるのが、国の重要有形民俗文化財にも登録されている押し舟。盆で研いで押し舟でじっくりと蜜を抜く、この作業を5回繰り返し、三谷製糖の和三盆が出来上がります。
「ここの土地以外でのサトウキビではできない。ここの土地でしか出来ないものなんです。」
畑に行く所から和三盆へ仕上げて行く行程までを同じ職人さんたちが一貫して行います。そんな職人さんたちの働き方も含め本当にこの土地でしかできない味を作り続けている、それが三谷製糖さんなのです。
三野製麺所がつくる乾麺は、乾燥しているので添加物を加えなくても長期保存が可能。さらに、ゆでればお店で食べるできたての讃岐うどんと同じのどごし、香り、コシが堪能できます。本場の味が楽しめるとあって、県外さらには海外から注文が来ることもあります。
「ゆでたうどんをそのまま乾燥させただけなんよ。シンプルでしょう?」と奥さんは言います。しかし、同じ作り方の乾麺を他では見たことがありません。なぜでしょうか。うどん作りの現場を訪ねました。

三野製麺所は今では乾麺と冷凍うどんの専門店となっていますが、最初は昭和初期に水車で小麦粉をひく製粉所として始まりました。「その頃のお客様は、ものご(入れもの)を持ってうどん玉を買いに来て下さり、子供のおつかいも多かったそうです。」と奥さんはおっしゃいます。
昭和40年ごろ、先代は「余った麺がもったいない。そうめんのように乾燥して保存しておけば欲しいときにすぐにゆでて食べられるのではないか」と思いつき出来たのが現在の乾麺です。
うどんは、ゆでてから時間が経つにつれて、コシとツヤがなくなってしまいます。三野製麺所の先代は、ゆでてしまったお店のうどんを捨てることなく、たくさんの人に食べてもらいたい、という食べ物への愛情や「もったいない精神」で、この乾麺を思いついたそうです。

乾麺をつくる現場を訪れたのは朝9時。すでにうどん生地はできていて、最後ののばしの作業を迎えていました。
「毎朝、4時くらいにはうどん生地を作り始めとるんよ」と奥さん。
発送用の、しかも保存のきく乾麺をつくるのに、なぜ早朝から作業を始めなければならないのでしょうか。
「手打ちうどんの行程はうどん屋さんと同じやけど、うちはさらにそれを乾燥させて、包装、発送するからね」
つまり、うどんを作る工程は、うどん生地作りからゆでるところまで、一般的なうどん屋さんと全く同じ。出来上がったうどんはその場で食べることができる状態のものです。ゆでたうどんをそのまま提供するのではなく、その後、全国、全世界へ届けるための工程があるため、早朝から作業を始める必要があるのです。
小麦粉と塩と水を混ぜ合わせて生地を作り、時間をかけて生地を寝かして、のばし、鍛えて、切る。その様子は昔ながらの手打うどん店そのものですが、三野製麺所ではところどころで機械を使っています。生地を平らにのばす機械はとても年季の入ったものでした。
「これは、うどん足踏み機といって、先代でもあるうちの父親が手作りした機械なんや」
先代はもともと機械製造の会社に勤めており、家業の製粉所を継ぎ、のちに手打うどんの世界に入ったそうです。

うどん生地を足踏みすることは、うどんのコシの生命線ともいえる大事な作業です。しかし、昭和40年代に「食べ物であるうどんを足で踏むのはよくない」という足踏み禁止令が出るという噂が広まり、先代は自ら設計して足踏み機を作ったそうです。




三野製麺所と他のうどん店との大きな違いは「ゆで時間」です。三野製麺所の乾麺は食べる前にもう一度ゆでるので、そのゆで時間も考えて乾燥前は通常よりもゆでる時間を短くしています。ゆであがったうどんを冷水で締めて、それを奥さんたちが手際よく1食ずつ計量して、乾燥用のざるにあげていきます。
「しっかり乾燥させないと、保存がきかないでしょう。けれど、乾燥しすぎると表面がひび割れしてしまうんよ」
そう笑いながら、奥さんはうどんの入ったざるを抱えて乾燥室へ入っていきました。この乾燥の行程は企業秘密だそうです。
しかし、三野製麺所の皆さんを見ていて、世界の人に愛されるうどんの秘密は、乾燥のしかただけではなく、「たくさんの人においしいうどんを食べてもらいたい」という想いなのだと感じました。

生地作りからお客様へのお届けまで、多くを手作業で行っているうどん作り。その製法は昔から変わることなく受け継がれており、手間暇のかかる、大変な製法です。けれど、その一つ一つの作業や手間を惜しまない愛情をかけたうどん作りが、古くは国鉄の時代から鉄道小包で遠方へうどんを届けていたという、全国、全世界にいる三野製麺所のファンを惹きつけてやまない魅力の一つでもあります。